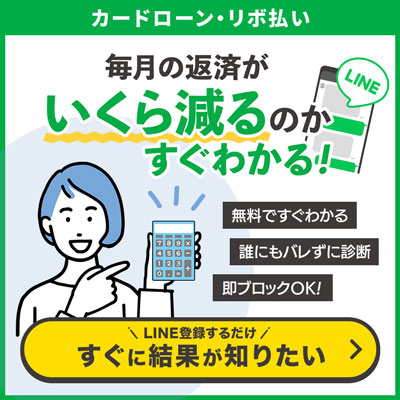借金の返済のめどがたたずに自己破産をした場合、価値が認められる財産は手放さなければなりません。それらの中には持ち家も含まれ、原則処分の対象となります。
しかし自己破産を検討したとしても「家だけは残したい」「家族と今の家に住み続けたい」と願う方もいるでしょう。
果たして自己破産をしても家を処分せずに手元に残す方法はあるのでしょうか?
この記事では、「自己破産 持ち家 どうなる?」と疑問を持つ方に向けて、持ち家を残せる可能性とその条件、注意点についてわかりやすく解説します。
自己破産すると持ち家はどうなる?
まずはじめに、持ち家は自己破産をした場合どうなるのでしょうか?
原則として持ち家は処分される
自己破産をすると、破産管財人によって「高額な財産」はすべて手放す必要があります。これらは破産管財人による処分のうえ換金され、債権者(お金を貸した人)への配当にあてられます。持ち家や車などはほとんどの場合、処分の対象になります。
特に、住宅ローンの残っている家は、ローンを組んだ金融機関の担保(抵当権)が付いているため、破産後にその家を差し押さえられてしまうケースが一般的です。
例外的に持ち家を残せるケースもある
ただし、すべての人が必ず家を失うとは限りません。条件によっては、自己破産後も持ち家に住み続けられる可能性があります。これは、「ローンの有無」「不動産の名義」「生活状況」などによって判断されます。
自己破産でも持ち家を残せる4つの条件
1.親族に買い取ってもらう
持ち家は自己破産をした場合は処分の対象となりますが、その際親族に売却して賃貸として住み続けるという方法があります。
ただし親族が買い取る場合は、破産管財人から厳しくチェックが入るため注意が必要です。そもそも自己破産の財産の処分の目的は債権者への配当であるため、親族だからといって市場価格よりも安く譲ることは避けなければなりません。相場よりも安く売却した場合、配当分を不当に減らしたと判断されてしまい、売買自体が認められなくなる可能性があります。
2.破産管財人に放棄してもらう
自己破産で処分の対象となる財産は「価値があると認められる」ものになります。そのため持ち家の立地が悪い場合や、建物自体の状態がいちじるしく悪い、更地にしなくてはならないが建物を解体するための費用が売買代金を上回ってしまう場合など、財産としての価値を認められないと判断された場合は、破産管財人が「放棄」する可能性があります。
放棄された持ち家は処分されず、管理処分権が自己破産をした本人にもどることになります。
3. 家族や第三者の名義で所有している
自己破産をした場合に処分の対象となる財産は「自己破産をする本人の財産」に限られます。そのため家の名義が本人ではなく、配偶者や親など第三者の名義である場合、その家は自己破産の対象財産にはなりません。つまり、差し押さえの対象外となるため住み続けることができます。
ただし自己破産をする本人が所有する家を、自己破産前に他者に名義変更したとしても、自己破産の対象財産から除外されることはないため、意味のない行為となります。
4. 不動産会社に売却してリースバックする
不動産会社に自宅を売却し、リースバックを利用するという方法もあります。不動産会社から賃貸する形で住み続けることが可能になります。リースバックを利用する場合、不動産会社との賃貸契約となるため毎月の賃料が発生します。そのため賃料を継続して支払えるかどうかを考慮する必要があります。また親族に買い取ってもらう時同様、売却価格が適正でなければなりません。
自己破産以外で持ち家を残す方法
自己破産は原則持ち家の処分が必要となりますが、自己破産以外の方法を選択した場合は処分する必要はありません。その方法は「任意整理」と「個人再生」になります。
任意整理
任意整理とは、借金の返済が困難になった場合に、裁判所を通さずに債権者(貸金業者など)と直接交渉して、将来の利息や遅延損害金をカットし、無理のない返済計画を立てる債務整理の方法のひとつです。
任意整理のメリット
- 将来の利息がカットされるため総返済額が減る
- 月々の返済額を減らせる
- 催促や取り立てがすぐに止まる
- 財産(家・車など)を失わずに済む
- 自己破産のような資格制限がない
任意整理のデメリット
- 元本は基本的に減らない
- ブラックリストに載るため、5年間は新たな借入れやクレカ契約が困難
- 返済を継続する必要があるため、安定収入がないと難しい
- 住宅ローンや税金、奨学金などは対象外になることが多い
個人再生
個人再生とは、借金を大幅に減額して原則3年(最長5年)で分割返済する制度です。裁判所を通じて行う法的な債務整理手続きのひとつで、特に住宅を守りながら借金整理をしたい人に適しています。
個人再生のメリット
- 借金が大幅に減る(利息だけでなく元本自体をカット)
- マイホームを残せる可能性が高い
- 自己破産と違い、資格制限(士業、警備員など)がない
- 安定した収入があれば認可されやすい
個人再生のデメリット
- 裁判所を通すため、手続きが複雑で時間がかかる(6か月前後)
- 手続き中・後に信用情報に事故登録される(いわゆるブラックリスト)
- 最低返済額の支払い義務があるため、無収入では利用できない
- 債権者の一部が反対すると失敗することもある
自己破産前に知っておくべき注意点
名義変更や財産隠しは違法になるリスク
自己破産の処分対象財産は「自己破産をする本人の財産」のみです。そのため、自己破産をする前に「家族や親族に名義変更をすれば手放さずに済むのでは?」と考えるかもしれません。
しかしこれは大変危険です。破産前の不自然な名義変更は、財産隠しの「詐害行為」として裁判所に認定される可能性があり、最悪の場合、自己破産が認められない事態もあり得ます。
家族への影響や保証人の問題にも注意
住宅ローンに親や配偶者が連帯保証人として関与している場合、自己破産するとその人に支払い義務が移る可能性があります。また、共働きでローンを返済していたようなケースでは、家族の生活にも大きな影響が及ぶため、全体のライフプランを見据えた判断が必要です。
持ち家を手放したくないならどう行動すべきか
専門家に早めに相談する重要性
自己破産を決断する前に、まずは弁護士や司法書士に「持ち家を残したい」という希望を明確に伝えることが重要です。条件さえ整えば、自己破産を避けて個人再生や任意売却で生活再建が可能なケースも多くあります。
家計の見直しや返済計画の再構築も検討
借金の原因が生活費の赤字や収入減である場合、まずは家計の見直しを行い、住宅ローンの支払いが続けられるかを冷静に判断することが大切です。
弁護士やファイナンシャルプランナーと連携して、無理のない返済計画を再構築することも家を守る手段のひとつです。
まとめ|自己破産後も家に住み続けるためにできること
自己破産をすると、原則として持ち家は手放すことになります。しかし、条件を満たせば持ち家を残せる可能性もあります。
特に「住宅ローン特則付きの個人再生」や「第三者名義」「任意売却+リースバック」などが有効な選択肢です。
無理に一人で判断せず、法律の専門家に早めに相談することが、家族の暮らしを守る近道になります。